
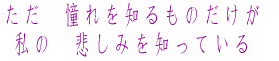
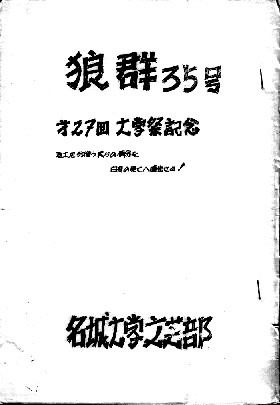 |
ガリ版印刷の 同人誌 狼群 35号です。 僕の本棚には 学生時代に作った ガリ版刷りの 同人誌 20冊ほどと 当時のビラ数枚が 棄てられずに 残してあります。 あの時代に 活字になれなかった 僕の散文たちを やっと 活字にして あげることができました。 さとちゃん |
病 気 佐藤 さと 外は木枯し ひうひうと。 凍った電線には 羽毛を逆立てた雀が二羽 とまっていた。 たかしの部屋には 隙間風が 建てつけの悪い窓枠から すうすう 入り込んだ。 たかしの寝ている蒲団の傍らでは チャンチャンコを着た たかしのおばあさんが まん丸の老眼鏡をかけて 縫い物をしていた。 「おとうちゃんは。」 「ん、起きてたんか。たかし。おとうちゃんは、 今夜も 仕事で帰らんて 言ってたで・・・。」 「おかあちゃんは。」 「向こうのうちで 内職を しとる。」 たかしの母親は たかしと別居していた。 伊吹おろしが ガラス窓を ガタガタと揺らした。 「おじいちゃんは。」 「納屋で ビクを 編んどる。 今日は 寒いもんで 畑にも 出てけぇへんわ。」 たかしは 入ると藁の匂いが ぷんぷんする薄暗い 納屋の土間で あぐらをかき 藁を叩いている 祖父の姿を想像した。 「準ちゃんは。」 「小学校から まだ帰って来ん。」 準ちゃんとは 家が一番近い同級生のことだ。 たかしは今日の給食のおかずが 先週みたいに 自分の大好きな ぜんざいだったら くやしいなと思っていた。 準ちゃんは学校帰りに 今日も僕の給食の分の パンとジャムを持って来てくれるのだうろか とも思っていた。 火鉢にのせられた 煤だらけの大薬缶から しうしうと 白い湯気がでるのを たかしは 凝視していた。 ーあの湯気が空に昇っていき ムクムクと白い入道雲や 黒い雪雲になり 雨や雪を降らすんだな。− と 理科の授業で習ったことを思い出していた。 そして 元気だった頃 皆と楽しく遊んだことも 思い起こしていた。 梅雨の頃も 楽しかった あの時は ひと月も 雨が降り続いた。 学校へ向かう田んぼ道が 田んぼの水に浸かっていた。 たかしたちは ぶかぶかの長靴をはいて学校へ行った。 途中で おのおの自分の長靴が どれだけの深さまで 耐えられるのかを競い合った。 たかしは無理をしたため 深みにはまり 長靴の中に水が どっと流れ込んでしまった。 一緒にいた皆が 笑った。 たかしは そのまま 学校へ行った。 水の入った長靴で歩くと ぐしゅっ ぐしゅっ という変な音をたてた。 長靴のなかに入った水は たかしの体温で温くなった。 それが気持ち悪かった。 一週間前に珍しく 雪が積もった。 しかし たかしは病気のため 外で雪と遊べなかった。 去年 雪が積もった時、 たかしは暗くなるまで 校庭に残り ひとりで雪玉を転がして 担任の石黒先生よりも背の高い雪だるまを作った。 校門のそばに でかい雪だるまを置いたので 翌朝 登校した皆が驚いていた。 一週間前に積もった雪はもう とけてしまっていた。 同級生達は どれくらいの雪だるまを作ったのだろうか。 少し 気になった。 たかしは 見ているだけの雪など ちっとも 楽しくなかった。 「ああ、早く 肺炎が なおらないかなぁ。・・・」 と 思わず声に出してしまった。 すると 膝の上で両手をもぞもぞさせて 縫い物をしていた祖母の手が止まり 「もうあと 三日たてば学校へ行けると 先生が言ってたで もう少しの辛抱じゃ。」 と 祖母が老眼鏡の奥から 目をしょぼつかせながら 言った。 ーもう、今朝から何度この言葉を聞かされたのだろう。 目が悪いので 針の穴に糸を通してあげるのは いつも 僕なのに・・・ 耳だけは 僕よりもずっとよく聞こえるのだから・・・・。− たかしには心配事がひとつだけあった。 ー鳩は帰ってくるだろうか。− たかしは一週間前に逃がしてしまった 茶ニビキと呼んでいた鳩のことを心配していた。 〔茶ニビキとは羽根の模様のことで 翼に茶色い二本の線がはいった鳩のこと。〕 たかしは鳩を八羽 飼っていた。 その朝 餌さを与えたあと戸を閉めるのを 忘れたため 鳩が全部外へ出て行ってしまった。 慣れていた七羽の鳩は 夕方までにちゃんと 鳩小屋の中に 戻ってきたのだが 茶ニビキだけは 戻ってこなかった。 たかしは 半年前 学校の帰りに畦道で血まみれになっていた 茶ニビキを見つけた。 たかしはポケットからハンカチを取り出し 傷ついた鳩の 翼の血を拭った。 そして 両手で抱きかかえて家に帰った。 家まで駆けて帰っていく途中 たかしは 両手のなかにある小さな生命のぬくもりと 生命の尊さを知った。 家に帰ってから 戦争の時、軍医と親しかったという 祖父に手当てをしてもらった。 祖父の手際よい処置は 鳩の生気を甦らせた。 祖父は 無口な人であった。 しかし 少々気難しいところがあり 時々 祖母に大声で怒る事があった。 田んぼに行かない時は たいてい 納屋で縄をなっていた。 疲れると煙管を取り出し いこいかしんせいをちぎって吸っていた。 たけしには 優しい祖父だった。 たかしのために 一日掛りで鳩小屋を増築してくれたのも 祖父だった。 学校から帰ってきても たかしには 遊び友達が少なかった。 遊び友達が塾へいってしまうと たかしは ひとりであった。 そんな時は 鳩小屋のなかで鳩を見て過ごしたり 慣れた鳩を外へ出して飛ばしたりしていた。 たかしは 自分の鳩がヒウヒウと風を切って 旋回して飛ぶ姿を 飽きずに眺めていた。 空を飛ぶ鳩を 見ていると 自分が鳩になって飛んでいるような 気持ちになった。 慣れた鳩は外に飛ばしても ちゃんと鳩小屋のなかへ戻ってきた。 たかしは もう少し慣れたら 茶ニビキも 飛ばしてやろうと思っていた。 そして 茶ニビキが家のまわりを 旋回して飛ぶ雄姿も想像していた。 しかし、逃げた茶ニビキは戻って来なかった。 たかしは学校から帰って来て 茶ニビキが戻って来ない事を知った たかしが学校へ行っている間の 出来事だったので たかしは 茶ニビキが風を切って飛ぶ姿さえ 見る事もできなかった。 その日は 暗くなるまで 屋根の上で 鳩の帰りを じっと 待っていた。 ー空を飛ぶことができたら きっと 見つけてやるのにな・・・・。ー たかしは 口惜しかった。 風邪気味のところへ 二時間も寒風に 曝されたのがいけなかった。 その夜から 悪寒に襲われた。 ー熱四十度二分。みみたぶが熱かった。 天井が右へ半回転。左に半回転。 勢いのついた天井は 大回転をし始めた。 目がまわる。 頬が火照っているのは薬〔トンプク〕 のせいだろうか。 そのかわりに胴体は寒くて たかしは ぶるぶる震えていた。ー お医者さんが来た。 懐中電灯で口のなかを覗き ステンレスのへらで舌を押さえつけられた。 黒い細長いゴム管の付いた聴診器を耳にかけて ポンポンと背中と胸を打診していた。 「本当に治るのだろうか。」 たかしは 不信そうに医者の顔を窺っていた。 ーたかしは 太い注射をお尻にうたれたけれども お尻なので注射の針が見えないから 少しも怖くなかった。ー 抗生物質をうっていったらしい・・・。 「肺炎になるかも・・・・。」 医者は帰りしたくを始めた。 祖母は 医者にぺこぺこ頭を下げてお礼を言っていた。 祖父は 心配そうにして たかしの寝床の傍らで 黙って正座したまま ほとんど動かなかった。 祖母は金色の洗面器に一杯 冷たい井戸水を汲んで来た。 そしてその水を搾った ぬれタオルをたかしの額へおいた。 たかしの父と母は別居していたため 来てくれそうもなかった。 たかしの熱は六日すぎても七日すぎても さがらなかった。 痰が気管につまりそうになり 苦しそうな息をぜいぜいと繰り返していた。 たかしには 二回目の医者の往診の記憶がなかった。 たかしが気付いた時 祖父がふとんの足元で たかしの足をさすっていた。 「どうして、足をさすっているの?」 たかしが聞くと 祖父は 「おまえの足が 死人のように 冷たくなっていたからな・・・。ずっと 意識不明だったでな。」 といった。 「イ・シ・キ・フ・メ・イ?」 たかしがというと 祖父はこっくり頷いた。 「おとうちゃんとおかあちゃんは・・・?」 たかしは 無理だと思ってはみたが祖父に聞いてみた。 「向こうの・・・うちに・・・・いる。」 祖父は言いづらそうに応えた。 「茶ニビキは?」 「思い出したら帰ってくるわ。 その時は友達もつれてくるじゃろう。・・・・」 ーたかしは不思議だった。 悲しくもないのに涙がでてきた。 病気になると 心が弱くなるのかな と その時 気付いた。ー チーン、チーン、チーンと 古いゼンマイ式の柱時計が三時を打った。 祖母は目をこすりながら まだ 縫い物をしていた。 「あと、三日か・・・・」 たかしは木枯しの音がする 窓の外を 子供らしくない淋しい顔つきで 眺めていた。 〔おわり〕 〔二十歳〕  |
次頁へ |

